労働分配率と一人当たり人件費の関係

サマリー
- 労働分配率とは、付加価値額に占める人件費の割合です。
- 労働分配率=人件費/付加価値額 で計算されます。
- 労働分配率は低いほど良いかといえば、そうではありません。付加価値額に対して人件費を一定水準以下に抑えつつ、従業員一人当たりの賃金を増やしていくという、低分配率・高賃金を実現することが、生産性向上の目的の1つです。
労働分配率とは
労働分配率とは、付加価値に占める人件費の割合のことです。計算式は次のようになります。

付加価値とは企業が新たに生み出した価値のことです。付加価値のうちどれくらいの割合人件費を支払っているかが、労働分配率です。※なお付加価値についてはこちらの記事もご参照ください→付加価値とは?
例えば次のような決算書があるとします。
| 売上高 | 1,000 |
| 売上原価(商品仕入) | 500 |
| 売上総利益 | 500 |
| 人件費 | 400 |
| 営業利益 | 100 |
この場合付加価値額は500、人件費は400ですので、
・労働分配率=400/500=80%
となります。一般的に労働分配率の基準は、50%以下で良好、60%程度で通常、70%以上だと高いとされています。
労働分配率は低い方が良いのか?
では労働分配率は低いほど良いかといえば、そうではありません。
労働分配率とは悩ましい指標です。経営者様としては、出来るなら社員に対して出来るだけ沢山の給料を支払いたい(=高賃金)という気持ちを持たれていると同時に、人件費は極力抑えたい(=低分配率)、という現実的な気持ちもお持ちではないかと思います。
次に、労働分配率と一人当たり人件費の4つのパターンについて説明します。
労働分配率が低く、一人当たり人件費が賃金相場より低い場合
低分配率・低賃金というパターンです。企業は人件費を抑えているため利益確保は出来ているということになります。しかし、生み出した付加価値に対して賃金が割安になっているということは、従業員のモチベーションに影響が出る可能性があり、人材確保の面で問題が起こる可能性があります。
労働分配率が高く、一人当たり人件費が賃金相場より高い場合
高分配率・高賃金というパターンです。従業員から見れば高賃金を得られているのでモチベーションは高まる可能性がありますが、企業は付加価値額に対して人件費を払いすぎている状態のため、収益性に問題がある状態です。
労働分配率が高く、一人当たり人件費が賃金相場より低い場合
高分配率、低賃金というパターンです。生み出す付加価値額が小さいために人件費割合が高く、しかし一人当たりの人件費は相場よりも低いということで、運営上危険な状態と言えます。
労働分配率が低く、一人当たり人件費が賃金相場より高い場合
低分配率・高賃金というパターンです。生み出す付加価値が高いため相対的に企業の人件費負担割合が低くなっているものの、一人当たり賃金は賃金相場と比べて高くなっているという状態です。企業・従業員双方がWin-Winになれる理想的な姿です。
労働分配率と一人当たり人件費の関係
以上の労働分配率と一人当たり人件費の組み合わせを図式化すると、次のようになります。

上図の左上象限のような低分配率・高賃金を実現できた状態が、生産性の高い状態といえるでしょう。






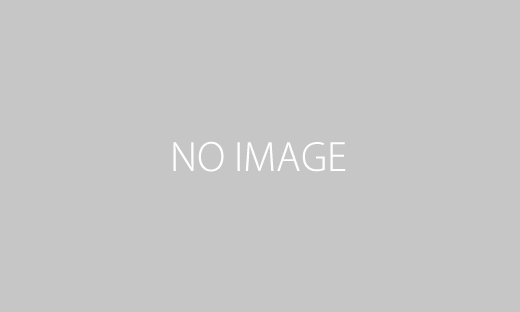





この記事へのコメントはありません。