会議の設計図をつくる~会議の成否は準備6割~


会議を成功させるには、事前に会議の設計図をつくる
会議の成否は準備で6割決まります。会議で良質なアウトプットを生み出すためには事前準備が欠かせません。事前準備には案内作成や会場設営、ツールの用意など様々ありますが、最も重要な準備は会議設計図をつくっておくことです。
会議設計図とは、会議進行の始まりから終わりまでのプロセス図です。ファシリテーターは、事前にこれを頭の中に叩き込んでおく必要があります。会議設計がないと、会議の場で頻出する“脱線・そもそも論・沈黙・暴論”のような変化球に対応できません。
会議設計図をつくっておくと、様々な変化球に対応することができます。議論が荒れたり脱線した時、素早く軌道修正をおこない、チームをゴールに導くことが可能となります。
議論の構成要素を組み立て、会議設計図をつくる
議論の構成要素とは
議論にはいくつかのタイプがあり、これを議論の構成要素と呼びます。議論は、次に挙げる5つの構成要素のどれかに当てはまります。
| ・共有 ・定義 ・解明 ・発散 ・収束 |
5つの構成要素がどんな議論なのかを次に解説致します。
共有
“情報や認識を共有する”ための議論です。例えば“会議の目的を共有・議論に必要な情報を共有する・決定事項を共有する」といったものです。
定義
“抽象的な言葉の定義を明らかにする”議論です。議論の中で使われる言葉の定義は大変重要です。言葉の定義があいまいだと、各自勝手な解釈に基づき議論を始めるため、かみ合わなくなります。
例えば“満足度を高める・浸透させる・スキルアップを図る”のような言葉です。こういった抽象的な表現は、
解明
“問題の真因を分析”する議論です。“売上が落ちているけどそれはナゼ?”というように「ナゼ?」から始まる議論です。そして“ナゼ?”を何回も繰り返して問題の真因を特定します。
発散
“解決策などのアイデアを多く出す”議論です。解決策や施策案を発見するために行われます。いわゆる“ブレインストーミング”のような形で進められる議論が発散です。
収束
“結論を出す”議論です。いくつかの選択肢から適切なものを選び、会議の結論をだす議論です。
会議設計図をつくる(例)
議論の構成要素が理解できましたら、会議設計図をつくってみましょう。作り方の基本は“会議がどう進行しそうか”をよく想像し、5つの構成要素を組み合わせることです。
ここでは実例をご紹介し、会議設計とはどんな感じのものか、感覚的にご理解頂ければと思います。
会議設計のない会議
議題「売上向上のため、どのような販売促進策を行うか」
もし会議設計なしにファシリテーターが「さあ皆さん、今日はこのお題について話し合いましょう」と会議を開始したとします。すると”とりあえずアイデア出しましょうか”という具合に“発散”の議論が始まります。もちろん発散の議論が始まること自体は問題ありません。しかし会議設計がきちんとされていないと、次のような展開が待っています。
A「俺は○○ていう取り組みをやったらいいと思う」
B「まあそうだね、俺もそれでいいと思う」
C「ちょっと待って、私は△△だと思う」
D「いやその前にさ、何で今の販売促進がダメなのかを考えるのが先じゃない?」
E「ていうか、そもそも売り上げ減少は販売促進のせいなの?営業はどうなのよ?」
このような経験をされた方も多いと思います。そして堂々巡りと脱線、疲労感が蓄積し、時間だけが過ぎていく・・・
会議設計の例
ではこの事例の会議設計例をご紹介します。ファシリテーターが事前に会議の流れを想像し、構成要素をどのように組み立てるのかをご紹介します。

このように、構成要素ごとに議論進行のイメージとそれに対するファシリテーターとしての対応を考えておきます。構成要素の“順番”、それから構成要素ごとの“ポイント”を整理しておくことで、議論が混乱した時にも軌道修正が可能となります。
もちろん会議はライブですので、設計図通り進行するとは限りません。むしろその通り進行することは稀です。しかし設計図があれば、“議論が迷子になって結局何も決まらなかった”、という最悪の事態を回避できる可能性は格段にあがります。
会議設計図をつくらずに会議に臨むのは丸腰で戦いを挑むようなものです。はじめは簡単でも構いませんが、社内でファシリテーターを務める方は必ず設計を行いましょう。
5つの構成要素ごとにファシリテーターが考えておくポイントはいくつかありますので、改めて別記事でご紹介致します。










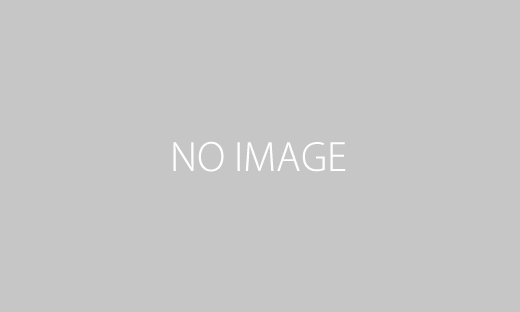
この記事へのコメントはありません。