問題の真因を解明する議論の注意点


真因訴求が上手く行かない原因
会議の議論にて問題の真因訴求が上手く行かず、結果的に良い施策が出ない原因には次のような理由が考えられます。
・問題に対する意識に違いがある
・問題の実態を具体的に把握できていない(感覚的な問題定義となっている)
・原因と結果の因果関係が整理されていない
これらの問題を解消するためには、議論の手順を正しく踏むことが大切です。
議論の手順
起きている問題の真因を訴求し、良い解決策を生み出すまでにはステップがあります。問題解決を図るには問題を様々な角度から検証する必要があるがゆえに、立場や職務の違うメンバーが議論し、その真因をあぶり出すことが必要です。その際会議ファシリテーターは、メンバーの持つ情報や知識を引き出す意味でも、次の手順を意識した会議進行をお勧め致します。
・問題定義
・ファクトファインディング
真因訴求
問題定義
問題解決の議論というといきなり“なぜ問題が起きているのか?”というWhyの議論から始めがちです。しかし問題そのものを議論参加メンバーが問題として捉えているのか、また問題は果たして本当に問題なのか、この点を明らかにする必要があります。
問題とは現状とあるべき姿のギャップを表します。例えば目標稼働率はクリア出来ているものの稼働率が下がっている、という事実があった場合、“目標稼働率をクリアしているから問題ではない”という認識もあれば“下がっているのだから問題だ”という認識もあります。
このように問題意識に違いがある状態で“なぜ問題が起きているか?”と議論しても上手くいきません。そもそも“稼働率が下がっている”という事実は問題なのかどうか、それを共有することが必要です。
名著「イシューからはじめよ(安宅 和人 著)」で述べられている通り、問題を解く前に何が問題なのか?を見極めることが、議論の生産性を高めるには極めて重要です。
そのためにはまず事象の“あるべき姿”を明確にしておくことが大切です。あるべき姿とは、
・いつ
・何が
・どの程度
達成されていることが理想の状態なのか、という問いへの答えです。
先ほどの“目標稼働率をクリアしているが稼働率は下がっている”状態が問題足りうるかどうかは、その事業の“あるべき姿”が何なのかによって変わります。
例えばありたい姿が“今期90%の稼働率をキープする”であれば、稼働率が下がっている事実は問題ではありません。しかし、「この事業は当社の次世代事業の柱と成長させるために3年後に市場シェア1位、売上高で○○億円を目指す」というあるべき姿が設定されていたら、今期目標をクリアしているとしても稼働率の低下は問題となります。
ファクト・ファインディング(What?Where?When?How much?)
問題を共有できたとしても、まだここから“なぜ”というWhyの議論には進めません。問題を共有することができたなら、その次にすることは“どこが問題か?”を特定することです。問題に対し、
・どこに問題が生じているのか?
・何に問題が生じているのか?
・いつ問題が生じているか?
・誰に問題が生じているのか?
・具体的にどのような問題が生じているのか?
という問いを投げ掛け、問題の実態を把握します。これをファクトファインディングと言います。脳は“一般化・抽象化・歪曲化”する傾向があり、また様々なバイアスがかかります。例えばある影響力の強い人の発言に強く影響を受けたり、直近あった出来事によって事実に対する認識が歪曲化されます。このような状態で「なぜ問題が起きるのか?」という議論をすると、早計で不確実性の高い結論となります。
例えば先程の“稼働率低下”という問題に対しては、次のような問いを繰り出し、データや事実に基づき実態を明らかにします。
・それはどの店舗で?稼働率の良い店舗と悪い店舗はどこ?
・稼働率が下がるのは週末?平日?
・来店数が減った顧客層はだれ?
そしてこれらの情報から問題個所を特定します。さらにこれらの情報から共通点と相違点に着目して問題の構造を発見します。例えば“週末に高齢夫婦の利用が減っているロードサイド店は稼働率が減少している”のように問題個所を絞り込むことで、その後の“なぜそうなっているのか?”という真因訴求の議論が活発化します。
さらに、“平日に高齢夫婦宇野利用が増えたロードサイド店は稼働率が増加している”という店舗があれば、それをベストプラクティスの1つとして、稼働率の高い店舗と低い店舗の違いが明らかになり、稼働率改善に活かすことができます。
真因訴求(Why?)
ファクトファインディングで問題の実態を把握したら、真因訴求を行います。真因訴求は主に次のようなステップを踏み、最終的に解決に取り組むべき真因を選択します。
・問題が生じている要因の要素を整理する
・要素ごとに真因を深掘りする
・深掘りした真因ごとの因果関係を整理する
真因訴求については、改めて別記事でご紹介致します。









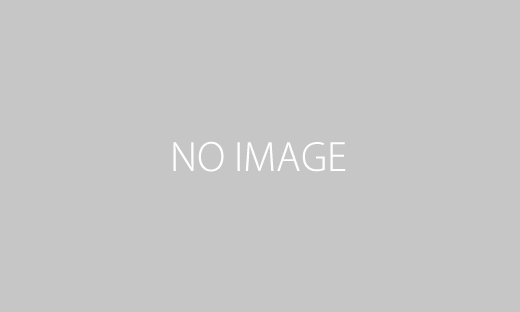

この記事へのコメントはありません。