売上分解式の作り方と活かし方


売上=客数×客単価
売上分解は、業種業態によってさまざまなやり方がありますし、一つの要素を更に細かく分解することもできます。本日は①売上分解式の作り方、①売上分解式の活かし方、について考えたいと思います。
売上分解式の作り方
売上分解式の例
売上向上を目的としてご支援させて頂いた小売業者様のケースをご紹介します。こちらの会社様は大きく2つのターゲット顧客を相手にしていました。1つのグループは地元のご高齢のお客様、もう1つのグループは観光客の方々でした。
この2グループは来店動機や来店頻度、購買商品が異ります。そのため売上分解式を2グループに分けて考える必要がありました。ここでは地元来店顧客の売上分解式をご紹介します。
●売上高=客数×客単価
●客数=新規顧客数+リピート顧客数(リピート回数)
●新規顧客数=商圏の人口×認知率×来店率×レジ通過率
●リピート顧客数=既存客数×来店回数×レジ通過率
●客単価=買い上げ点数×商品単価
●買い上げ点数=動線長×売場立寄率×商品視認率×商品取り上げ率×商品買上率
今回のご支援ケースでは以上のような分解式を作り、問題点の洗い出しと改善策を考えました。分解公式は様々な形で作れます。
例えば
・客数=来店客数×買上率
・来店客数=通行客数×入店率
のような式も成り立ちます。
成果に結びつく売上分解式を作るコツ
売上分解式の作り方で押さえておきたいことは「業種特性」と「ターゲット顧客」です。業種特性やターゲット顧客が分かると、売上構成要素の中で何が重要なのかが明らかになります。そして重要な売上構成要素を細かく細分化していきます。
例えば、事例のご支援先は食品やお土産などの小売店であり、限定された商圏でのビジネス(観光客除く)でした。つまりどちらかと言えば粗利益率よりも回転重視であり、来店客数(新規獲得とリピート回数)や買い上げ点数(買い物カゴに入れた商品数)が業績に大きく影響する業種のため、この2点を重点的に分解していきました。
来店客数に関しては新規獲得とリピートに細分化しました。またエリアビジネスであることも考慮して、商圏内の人口を売上分解式の起点としました。
買い上げ点数に関しては非計画購買を促進するために、インストアでの顧客行動を計算式に置き換えました。すなわち、顧客が店頭に入ってから取る行動を「動線の長さ→カテゴリー別売り場への立ち寄り→売り場内での商品視認→カゴに投入」に分解して算式としました。
売上分解式の活かし方
分解した売上要素からそれぞれの問題点を洗い出す
分解をしたら売上要素を数字で具体的にしますが、あまり厳密にやろうとするとデータの取得に時間がかかるものもありますし、そもそも数字で表現出来ない要素もあります。大切なことは分解した個々の売上要素をターゲット顧客にフィットするよう改善していくことです。そのため下記のようなざっくりとした3段階評価で判定するのもお勧めです。
以下の表が分解要素を3段階判定した結果です。
| 売上要素 | 判定 | 問題点 |
| 商圏の人口 | △ | 減少傾向 |
| 認知率 | × | 既存顧客以外へのプロモーション等アプローチがほとんどない |
| 既存客数 | 〇 | 店頭顧客調査により、ほぼリピーターであることが判明。(ID-POSは導入していない) |
| 既存客来店回数 | △ | リピートは平均月2回程度で、それ以外の日は競合他店に来店している可能性が高い。 |
| 動線長 | × | レジ前や入り口で導線が錯綜している、また回遊を促すレイアウトとなっていない |
| 売り場立寄り率 | △ | 商品群のカテゴリー分けに問題があり、欲しいものがどこにあるのか分からない |
| 商品視認率 | △ | 注目商品や販売重点商品の魅力訴求が十分でない |
| 商品取り上げ率 | △ | ターゲットである高齢者にとって手に取りにくい棚割り |
「改善策の立案」と、「効果」「実現難易度」から取り組む優先順位をつける
3段階判定をして問題点を洗い出したら、それに対する改善策を考えていきます。
| 売上要素 | 効果 | 実現難易度 | 改善の方向性 |
| 商圏の人口 | 高 | 高 | 改善困難 |
| 認知率 | 高 | 低 | 高齢顧客にリーチする情報媒体で、ターゲットに訴求するメッセージを発信 |
| 既存客来店回数 | 中 | 中 | ポイントカードの還元率、ポイント還元率UPデー、ポイント使用可能最低ポイント数の見直し |
| 動線長 | 高 | 中 | マグネット商品の計画配置や入り口から店奥まで見通しの良いレイアウトに変更 |
| 売り場立寄り率 | 中 | 中 | 商品カテゴリーの見直しと、通路幅の拡大 |
| 商品視認率 | 中 | 中 | 重点商品についてPOPによる訴求や、スタッフの商品説明力強化 |
| 商品取り上げ率 | 中 | 低 |
棚やワゴンの工夫や、ターゲット層に売れている商品の棚割の工夫 |
改善策は「効果」「実現難易度」で優先順位を付けます。「効果」は売り場平米当たりの粗利額(売り場の収益力)や交差比率(商品の収益力)など、業績に直結する指標への影響度の大きさで判定します。「実現難易度」は施策の実現がコスト面、ノウハウ面などから企業様にとって実現しやすいかどうかで判定します。
こちらの企業様の場合、客数においては新規客数を増やすことがもっとも喫緊かつ重要な対策でしたが、幸い新規客を増やすためのターゲットへ訴求力の強い媒体出版社との強いコネクションがありました。
「買い上げ点数」に関する「動線長」「売り場立寄り率」「商品視認率」「商品取り上げ率」は、ターゲット顧客層が明確になっていたため、様々なアイデアが出ました。今回のケースでは地元の高齢顧客で病院帰りに利用する顧客が多い、ということまで分かっていましたので、健康維持商品や地元品の魅力訴求や、コミュニティとしての側面を持たせていく施策を考えていきました。
まとめ
1.売上を分解するときは、企業様の「業態」と「ターゲット顧客」を押さえる
2.分解して売上要素を明らかにし、要素ごとの問題点抽出と3段階評価を行う
3.改善策を立て、「効果」と「実現難易度」の2軸から優先順位を決める
売上分解式は様々な業種業態で活用できる便利な概念です。売上向上を考える際にはぜひ参考になさって頂ければと思います。
より詳しくご相談なさりたい、という方はこちらからお問い合わせくださいませ。







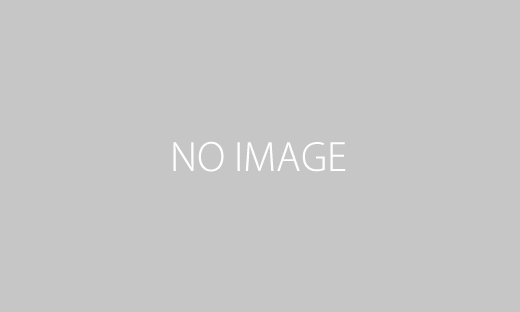



この記事へのコメントはありません。